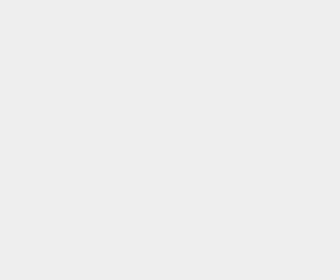富士フイルムのカメラを購入して、次にXマウントのレンズは何を買おうと思って候補に上がるのは「FUJINON XF35mmF1.4 R」でしょうか。
「FUJINON XF35mmF1.4 R」は2012年にレンズ交換式のXマウントが立ち上がった時に発売された3つのうちの1つで、いわばXマウントの御三家的なレンズです。その分発売から多くの人がこのレンズに触れ、Xマウントの印象を決めた一本だと思っています。
今回はそんな「FUJINON XF35mmF1.4 R」を私の視点と作例を交えてつらつらと書いてみたいと思います。
「XF35mmF1.4 R」

X-Pro1とXF35mmF1.4 R。統一感のある黒の筐体に金属のレンズフードが似合います。初期に発売された「XF35mmF1.4 R」「XF18mmF2 R」「XF60mmF2.4 R Macro」はどれも専用の金属フードが採用されており、このフォルムも合わせて好きな人が多いと思います。私も多分に漏れず大好きな1人です。
仕様と比較
aEマウント
[35mm判換算]53 - 53mm相当
[35mm判換算]53 - 53mm相当
[35mm判換算]48 - 48mm相当
(非球面レンズ1枚 HT-EBCコーティングレンズ)
(非球面レンズ : 2枚 HT-EBCコーティングレンズ)
(標準0.8m~∞ マクロ28cm~2.0m )
(35cm - ∞)
選ぶ際に悩むのが XF 35mm f2 WR だと思います。両方のレンズを使用しましたが、XF 35mm f2 WR の描写は比べるとややコントラストが高く硬質です。XF 35mm f2 WR は後発なだけあり XF35mmF1.4 R にはない点として、防塵防滴でインナーフォーカス、ステッピングモーターなのでAFが静かで高速。絞り羽根は9枚といった改良が加えられています。
以外と重量は変わらず、XF35mmF1.4 R はF1.4という明るさを持ちながら軽量となっているのも大きな特長だと思います。
いいところ
- f/1.4の明るさ
- 大口径レンズにしては187gと軽い
- 開放からシャープで繊細な描写
- 絞っても描写が安定していて使いやすい
- ボケが柔らかい
- 逆光に強い
- ピントリングが大きくピント合わせがしやすい
- 専用の金属フードと合わせて格好いい
大は小を兼ねるとも言いますが、f/1.4の明るさの大口径レンズは持っていて頼もしい存在です。開放から抜群の解像感と、柔らかいボケ、逆光にも比較的強く、どんなシーンでも安心して撮影することができます。
気になるところ
- フリンジが出やすい
- 最短撮影距離付近の近接の描写が甘い
強い光源や、明暗差のある場面で細い線を撮影した場合に、紫や緑のフリンジが発生します。電子シャッターのおかげでお昼でも積極的に開放で撮影できるようになりましたが、その影響で本来ならあまり気にする必要がないシーンでも発生することが多々あります。絞れば改善するので意識的に絞りたいところです。
また、近接時に開放で撮影すると描写が甘く感じます。ネガティブな要素ではなくふわっとさせたい時は覚えて置いたほうが良い要素でしょうか。寄るためのレンズではないですが使う場面も多いので、寄ったときは絞ると覚えておいた方がいいと思います。
悪いところ
- 電子制御式のフォーカス制御の影響か、シームレスなフォーカスの移動ではなくステップ式。特に近接の撮影で注意が必要。
- フードの先に取り付けるキャップがシリコンでカバンの中で迷子になる。
富士フイルムのレンズ全般に言えることですが、電子的なフォーカス制御の影響でフォーカスの送りが「無段階」ではなく「ステップ式」になっています。遠景では気になりにくいですが、近接時では細かいピント合わせが必要な場合に、合わせたい箇所の前後に合焦することが良くあります。ピントが「無段階」ではないので、体で前後して合わせる必要が出てきます。描写の癖と相まって、最短撮影距離付近での撮影はやや注意が必要かと思います。
ちなみに金属フードの先に取り付けるキャップはシリコン製でかぶせるタイプです。撮影時はキャップをしないので問題ないですが、しまうときはカバンの中で外れやすくてだいたい迷子になってしまいやすい残念仕様。色々悶々としましたが以下の記事がベストソリューションでした。
しょうがないところ・評判ほど気にならないところ
- AF速度は遅めだけどいうほど気にならない。速度・精度はボディにも依存
AFはDCモーターなので、ガガガっといった音が出ます。速度はお世辞にも早くはありませんが、極端に遅すぎる。といったこともないと思います。
富士フイルムのAFの特長ですが、別段このレンズのAF精度が悪いわけではなくボディ側の影響が大きいです。現にX-Pro1と比べると、X-T2、X-T20で使用した際はAFの速度は大きく変わり、現行のX-T3、X-T4に装着すれば別のレンズと思うほど精度が向上し、合焦するまでの時間が短縮されます。
動いている人物などを追従して撮影する場合は、X-T3以降のカメラと合わせるのがおすすめです。
「XF35mmF1.4 R」で撮影した写真をみる
繊細で緻密な描写とやわらかなボケ
太陽の光が柔らかく射し込む様子をしっかり捉えてくれています。「アウトフォーカスのボケの美しさ」を追求したとの言葉にも納得の描写です。ピントが合った面がシャープなので、柔らかいボケと相まって、ソフトな描写でありつつ立体感を楽しめるレンズになっています。

少し絞ればキレッキレの描写が楽しめます。開放の柔らかさと絞った時の解像感。素晴らしいレンズです。
使っていての私の感想ですが、「XF 35mm f2 WR」や「XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS」よりも優しい描写なので、色がはっきりしやすいフィルムシミュレーションが良く似合っていると思います。
最短撮影距離は28cm、最大撮影倍率は0.17倍です。なんとかテーブルフォトもできる距離でしょうか。マクロ的な使い方は難しいので、同時に発売されている「XF60mmF2.4 R Macro」との棲み分けがしっかりできているのも丁度いいと思います。
絞り羽は7枚の円形絞り。とてもきれいな玉ボケです。
背景を残したかったのでF4まで絞って撮影してみました。絞っていてもとろけるアウトフォーカスが気持ちいい描写です。

APS-CのセンサーでもF1.4の明るさがあれば十分にボケますね。周辺の減光はカメラのボディ側で補正されてしまうので意識することはないはずです。
絞り開放から解像感のある描写
本レンズは「全群繰り出し式」というピントの位置によってレンズが移動する機構を採用し、画質面に拘った構成になっています。他メーカーでも、例えば画質に定評のある「Nikon AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G」などのレンズも見た目はインナーフォーカスを装っていますが「全群繰り出し式」を採用しています。
AF面ではミラーレスカメラ時代のレンズでは記憶がない程に「ガガッガガガ」っといったモーター音が鳴り響きく愛嬌は抜群な個性を持っています。個人的にはこれが好きなんですが、速度、音で気になる方も多いようなのでチェックしておくポイントでしょうか。動画の撮影で使うとAF音がもろに入ってしまいます。
暗いシーンですがF1.8で夜景を撮影してみました。絞り開放でも中央部は抜群の解像度なので、夜景でも積極的に撮影することができるのが嬉しいですね。
強い光源などはフリンジがやや目立つ

強い光源をが画面に入ってくると、光源の周りに軸上色収差の紫や緑のフリンジが現れます。絞れば問題ありませんがこの点は特に注意でしょうか。
特に顕著な例がこちら。枝の周りに紫と緑のフリンジが盛大に現れています。太陽を左に配置して意図的にハイキーで撮ったものです。電子シャッターがなければなかなかできない一枚ですね。太陽を入れていますが大きなフレアやゴーストはあまり発生しません。
「FUJINON XF35mmF1.4 R」で撮影した作例いろいろ
このレンズは少し絞るだけで周辺もズバッと解像します。遠景だとf/2.8でも十分すぎる程シャープですね。癖玉に慣れている人はあまり面白くないイメージを持ってしまうかもしれませんが、どの絞り値、シチュエーションでも画に安定感があるので扱いやすいレンズだと思います。
f/1.4の大口径レンズですがコンパクトで187g(フード除く)と軽量です。いつでもカバンに忍ばせておけるのも大事なポイントですね。

F1.4だとこの距離でも手前がボケています。周辺がやや滲んでいますが、使い方次第で楽しめる描写です。
とろける後ボケに比べると、ほんの少しだけ残存性のある前ボケでしょうか。
f/11まで絞って光芒で遊んでみました。富士フイルムのレンズってどれもウニウニしますよね。



陰影の描き方がたまりません。幹のディテールもとてもリアリティを感じますね。世代を超えて進化する「X-Trans」センサーの恩恵もひしひしと感じた一枚です。

敢えて言えばオートフォーカスが弱い癖に、マニュアルフォーカスが使いやすい訳ではないところでしょうか。ピントリングは幅があるので操作がしやすいですが、やや軽いストロークで気持ちよさがないのが残念です。

好きな一枚です。f/4~f/5.6まで絞った時の繊細で緻密な描写。ローパスフィルターレスなんて必要ないと思っていましたが、こんな写りを見てしまうと考えが改まります。


繊細で緻密な描写とやわらかなボケが楽しい FUJIFILM XF35mmF1.4 R
FUJIFILM XF35mmF1.4 R はとろけるアウトフォーカスのボケを使った柔らかい表現と、絞ったときの繊細で緻密な描写で絞る楽しみも味わえるレンズだと思います。大口径F1.4のレンズで、それでいて比較的手が届きやすい価格を実現しているのは、APS-Cセンサーを生かした小型、軽量のフォーマットを選んだ富士フイルムならではでしょうか。
初めての単焦点にも次の一本にももってこいなこの一本ですが、逆にこれが最初だと、他のレンズを使った時や、癖のあるレンズを使った時に苦労するかもしれません。発売してすでに7年が経過しましたが、色褪せるどころか世代を重ねたボディによってまだまだ魅力がましていくような気もします。
どのマウント使っていても必ず使ってきたこの画角。フォルムも合わせてお気に入りのレンズの一本です。